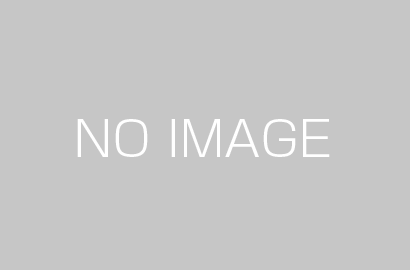UNIVEX MERCURY
製造・販売元のUniversal Camera Corporationは1930年ごろに安価なカメラな販売で成功しました。
1938年から製造されたMERCURYはフラッシュシンクロを内蔵した世界初のカメラで、ロータリーディスクシャッターに起因する独自なフォルムとともにシャッタースピードも1/1000を実現するなど、突出した機能を有していました。
光学的にも戦前にF2台の製品はKODAKのバンタムスペシャルとエクトラの3機種のみでした(多分)。
オリンパスより20年も前のハーフカメラ、ロータリディスクシャッターですが、UNIVEXは1936年ごろに映写機で大ヒットしたメーカーなので実績は十分で、80年後の現在でも実用可能な機種が多い堅牢な造りです(バネはヘタってますが)。
初代(戦前)の、MERCURYはUNIVEX200シリーズというギア付きスプールの今日では入手できないフィルムを採用していました。MERCURY IIでは135フィルム用に寸法的に大きくモディファイされました。
MERCURY I (Model CC)
初代MERCURYはギヤ付きスプールのUNIVEXのフィルムが必要で、巻き戻し機能もなく、ブラックバッグでフィルム取り出しをする必要がありました。
ストロボも独自サイズの専用のものが必要です。
フィルムが入手できないので現在はコレクション・観賞用です。
主な仕様
- 名称:MERCURY I
- 分類:ビューファインダーカメラ
- 型式:35ミリロータリシャッター式ハーフサイズカメラ
- 適合フィルム:Univex 35mmロールフィルム
- フィルム送り:巻上げのみ
- フィルム計数:順算式,最大65枚まで
- 画面寸法:24×18 mm
- 適合レンズ: TRICOR f2.7 F=35 mm TRICOR f3.5 F=35 mm HEXAR f2.0 F=35 mm 他に75mm、125mm
- ファインダー:ガリレオ
- 距離調節:手動設定,最短撮影距離1’-6’’(約45 cm)
- 露出調節:手動設定,f2.7-22
- シャッター:ロータリ式フォーカルプレン,T,B,1/20~1/1000秒
- シンクロ接点:あり,ホットシュー(現在のストロボには適合しない)
- 電池:不要
- 質量:約530 g
- 寸法:約138 H×88 W×60 D〔mm〕(突起物を除く実測値)
- 発売年:1938(昭和13)年
- 製造・販売元:Universal Camera Corp.
主な特徴・注意点
- シャッタースピードはディスクシャッターの回転力に依存
- 定期的なメンテナンスは欠かせないが、シャッタースピードコイルバネに依存するのでは年々遅くなる傾向にある
- グッタペルカ(貼革)をはがさずに分解できます
- 専用スプールが必要
- 専用ストロボが必要
UNIVEX MERCURY II (Model CX)
主な仕様
- 名称:MERCURY II
- 型式:35ミリロータリシャッター式ハーフサイズカメラ
- 適合フィルム:135判
- フィルム送り:巻上げ,ノブ巻き戻し
- フィルム計数:順算式,最大65枚まで,手動リセット
- 画面寸法:24×18 mm
- レンズ:UNIVERSAL f2.7 TRICOR F=35 mm
- ファインダー:逆ガリレオ(?)
- 距離調節:手動設定,最短撮影距離1’-6’’(約45 cm)
- 露出調節:手動設定,f2.7-22
- シャッター:ロータリ式フォーカルプレン,T,B,1/20~1/1000秒
- シンクロ接点:あり,ホットシュー(現在のストロボには適合しない)
- 電池:不要
- 質量:約600 g(実測)
- 寸法:約940 H×142 W×54 D〔mm〕(突起物を除く実測値)
- 発売年:1942(昭和17)年頃?1945(昭和20)年?
- 製造・販売元:Universal Camera Corp.
- シャッタースピードはディスクシャッターの回転力に依存
- 定期的なメンテナンスは欠かせないが、シャッタースピードコイルバネに依存するのでは年々遅くなる傾向にある
- グッタペルカ(貼革)をはがさずに分解できます
- 専用スプールが必要
- 専用ストロボが必要
ギャラリー
MURCURY I




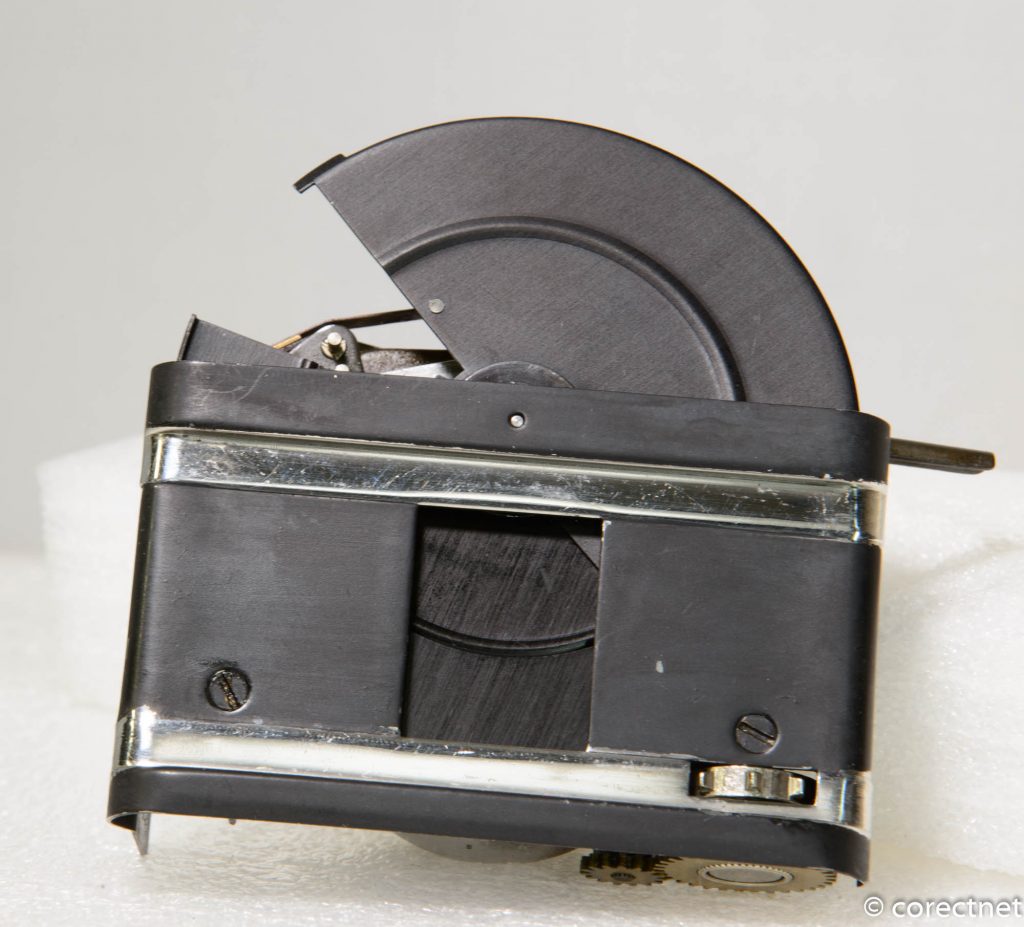













MERCURY II